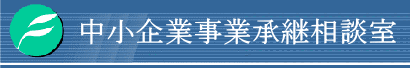事業承継対策の必要性
下の図のとおり、定期的に社長が交代する大企業と比べ、中小企業の社長の平均年齢は年々確実に上昇しています。15年間で約4歳上昇し、 この傾向は今後も継続することが予想されます。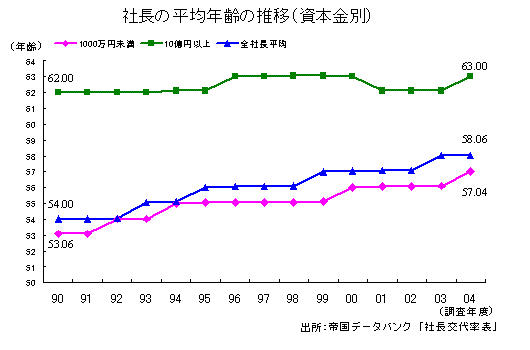
また一方で、中小企業のオーナーはバイタリティに溢れる方が多いため「自分が元気なうちはまだまだ大丈夫」と考え日々の業務を優先するあまり、 事業承継対策を後回しにしてしまいがちですが、統計的には下の図のとおり60歳を経過した頃から生存率は急激に下降をはじめ、そして身体の不調は 予告なしにある日突然やってきます。このことからも早めに事業承継対策に着手することが重要と考えられますが、正に事業承継対策はオーナーの引退が 前提となる事案なだけに、周囲人からは勧めづらいという側面を持っています。つまり、オーナー自身の決断が重要となるのです。
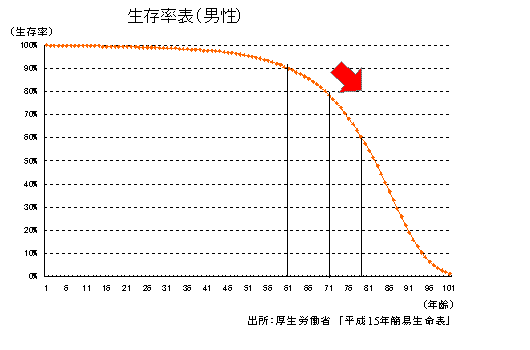
中小企業を取り巻く事業承継の『後継者不足』という問題点
中小企業オーナーが事業承継対策を考えた場合、まず問題となるのが昨今の『後継者不足』です。下の図のとおり、20年前は9割以上が親族内での承継でしたが、 年々親族外への承継が増加しており、現在は実に4割近くが親族外への事業承継となっており、この傾向は今後も加速することが予想されます。 つまり、以前であれば当然親族内に承継者がいることが規定路線だったわけですが、現在においては『誰に、どのように』事業を承継させるかといったところ から検討しなければならないのです。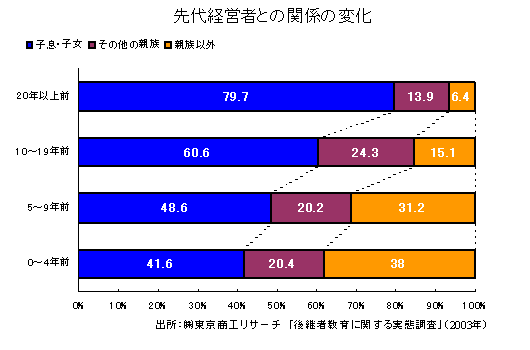
事業承継対策の重要性
中小企業の場合、オーナーの信用によって事業が運営されている場合が多いものです。 金融機関はオーナーの経営能力や実績(もちろん所有資産もですが)に対する信用に基づいて貸付を行っていますし、お取引先もオーナーに対する信用に基づいて 支払条件などが決まってきている場合が多いわけです。このような状況の中、ある日突然オーナーがいなくなるといったことが生じれば、金融機関やお取引先は不安になり、結果として取引条件が厳しくなったり、場合に よっては借入の一括返済を求められたりするといったことが生じるかもしれません。
また、対策が不十分のまま相続が発生することとなれば、多額の相続税を負担することとなり、個人で払いきれない場合には会社で借入を起こして相続人に貸付ける ことにより納税しなければならないような状況となることも考えられます。
さらに、もともと後継者不在だった場合には、とりあえず相続人の誰かが代表を引き継ぎ、実際の事業は今まで番頭格だった方の肩にのしかかってくるといった歪な 状況となってしまい、会社の運営自体がぎこちなくなってしまうかもしれません。
こういった状況が続き、最悪の場合には今まで順調だったにもかかわらず、事業承継をきっかけとして会社を畳まざるを得ないといったことになりかねません。
会社を清算するとなれば、相続人にかかる負担はもちろん、会社の従業員やお取引先にまで多大な迷惑がかかることとなってしまうのです。
このような事態を避けるためには早めの事業承継対策しかありません。 後継者を育て、金融機関やお取引先からの信頼を得て、もしくは外部から後継者を迎え入れる準備を整え、できるだけ早い時期に来るべき事業承継の準備をしておく 必要があるのです。
そして、この決断は他でもないオーナーに残された最後のハードルでもあるのです。
私どもはこの最後のハードルを乗り越えるお手伝いをしたいと考えております。
初回無料相談を承っておりますので、ぜひ一度お気軽に相談ください。
大野木総合会計事務所
担当:池田
TEL:03-5570-8744
Mail:mainfo@ohnogi-cpa.co.jp