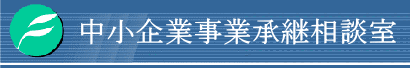事業承継の3つの選択肢
中小企業の事業承継には、誰を後継者にするかによって大きく分けて3つの選択肢があります。また、どの方法を選択するかによって対策の課題や内容は変わってくることはもちろん、時には全く逆の対応をとらなければならないこともあります。
例えば、相続を前提とした承継を考えた場合は相続税の負担を少なくするため、できるだけ株式の評価額を低くできるかを検討しなければなりません。 これに対し、M&Aを考える場合にはオーナーの手取額を増やすためにできるだけ株式の評価額が高くなるよう対策をとる必要があるのです。
したがって、オーナーは会社の状況を十分に分析・理解して、どのような方法で会社を承継するのかを慎重に検討する必要があるのです。
【選択肢1】 親族を後継者とする場合
親族内に後継者候補がいる場合には、後継者教育と株式の移転が主な課題となります。社内の各部門を経験させ、グループ子会社の経営を任せるといったことを通じて、経営者としての能力を身につけさせるとともに、どうしても不足する部分にはサポートするための 人材登用といった組織体制を整えることで、後継者に事業を引き継ぐ体制を整えます。
一方で不採算事業を整理して損失を計上したり、役員退職金を支給するといったことを計画的に行うことにより、一時的に会社の株価が下がったタイミングで株式を後継者に贈与・ 譲渡することにより効率的に後継者に株式を移転するといった方策を検討します。
また、相続が発生した場合に事業承継税制の適用を受けることにより一定額の相続税の納税猶予を受けることも可能です。
【選択肢2】 親族外の従業員、もしくは外部から後継者を招聘する場合
親族内に後継者がいない場合には、親族外の従業員に承継するか、もしくはオーナーの知り合いなど外部から後継者を招聘することを考えます。親族外の従業員に承継させる場合には比較的社内での反発は少ないと思われますが、経営者としての素質を持った従業員がいるかという問題があります。
逆に、経営の素質を有する人を外部から招聘する場合には今までと異なるやり方を推進することなどにより社内から思わぬ反発が生じたりすることが考えられます。
また、いずれの場合にも株式をどのように後継者に承継させるかといった問題が生じます。中小企業では過去の利益を配当することなく社内留保していることが多く、株価も高く 算定されることが多いのですが、通常、親族外の後継者や外部からの後継者候補の方は株式を買い取るだけの資金を有していることは稀であるのです。
このような場合には金融機関からの支援やファンドの活用といった方策を検討する必要があります。
【選択肢3】 M&Aにより他社に経営を委ねる場合
親族にも、従業員にも、知り合いにもどうやら会社を承継させるに足る人材がいなかった場合はどうなるでしょうか。このような場合になりますと「もう会社を清算するしかない」と思いがちですが、そうではありません。
株式を同業や周辺事業を行っている他社に売却して、経営自体を委ねるという方法があります。いわゆるM&Aと呼ばれているものです。
M&Aというと新聞紙上を賑わしているような大企業のお話で、中小企業には関係ないと思われるかもしれませんが、実際には件数でいえば中小企業のM&Aの方が圧倒的に多いのです。
「うちの会社を買ってくれる会社なんてあるはずないよ」と思われるかもしれませんが、特定技術に秀でていたり、商圏を広げたいというニーズにマッチしたりと様々なニーズ に合致することによって、実際、中小企業のM&Aは頻繁に行われています。 M&Aが成功すれば、従業員の皆様の雇用も守られますし、上場企業の一部門として再出発することになり従業員の皆様にも喜んでもらえたといったケースもあります。 したがって、最初から清算を考えるのではなく、時間をかけて会社を磨き上げM&Aの機会を窺うというのも事業承継の一つの方法なのです。
まずはご相談ください
どのような形で事業承継を進めていくかについては、後継者候補の有無、会社の状況、資金調達の可能性など様々な要因によって異なってきます。初回無料相談を承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
大野木総合会計事務所
担当:池田
TEL:03-5570-8744
Mail:mainfo@ohnogi-cpa.co.jp